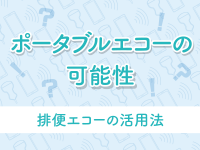エンバーミングの手順とは? 専門的な処置について解説

エンバーミングには、大きく分けると「防腐」「消毒」「修復・化粧」の3つの目的があります。今回は、これらの目的のために、実際にどのような処置が行われているのか、現役のエンバーマーである牛渡一帆氏に解説していただきます。
目次
エンバーミングの手順
エンバーミングは、体内・体外、両方からのアプローチによってご遺体の状態を安定させ、感染症に対する安全な環境をつくり、お姿を整える処置です。エンバーマーは、こうした処置を通じて、ご遺族が安心して最後のお別れに向き合うことができるよう支援しています。
エンバーミングは、大まかにまとめると次のような手順で行われます。
| 1. ご遺体の施設への受け入れ、必要書類やお預かり品の確認 2. ご遺体体表の汚れの洗浄・消毒および状態確認 3. 薬液の調合 4. 表情の整え 5. 血管の剖出 6. 薬液の注入・排血 7. 胸水や腹水、体腔内残渣物などの吸引 8. 体腔内への薬液充填 9. 各所切開部の縫合 10. 全身の洗浄・洗髪 11. 治療痕や点滴痕などの処置 12. 着せ替え 13. 表情の再調整・メイク 14. ヘアセット 15. 布団への安置または納棺 |
通常、処置に要する時間はおおよそ3時間ですが、ご遺族の要望や故人の体格、身体の状態によっては時間が前後したり、処置内容が追加されたりする場合もあります。広範囲にわたる損壊や欠損などがある場合では、丸一日お預かりすることもあります。
次に、エンバーミングの専門的な処置について詳しく解説していきます。
ご遺体に対する専門的な処置の実際
薬液の注入・排血
通常、生体では体内に取り込まれた酸素や栄養、水分は、動脈血によって全身の組織に運ばれ、各臓器で代謝や処理が行われます。そして、その過程で生じる二酸化炭素や老廃物、余分な水分は静脈血によって回収され、最終的に呼気や便、尿として体外へ排出されます。エンバーミングでは、この脈管の機能を利用し、動脈からの薬液注入と静脈からの血液排出(排血)を行います。
動脈を流れる薬液は、組織に作用し、防腐や消毒、血色をよくするといった効果を与え、静脈に入ると、残留している血液とともに老廃物や余分な水分など、腐敗の元になるものと混ざり合って流れていきます。
しかし、生体と違い代謝機能が失われているご遺体は、自力で不要な物質を体外へ排出することができません。したがって、静脈の一部を開放し、直接体外へ排血する必要があります。
薬液の注入に使用する動脈には、基本的に頸部や上腕、大腿にある血管を選択し、左右いずれか一側、または複数の箇所を切開します。排血には右内頸静脈を使用することが多いです。ただし、血流が滞るような障害(動脈硬化や血栓など)がみられる場合は、該当箇所に皮下注射で薬液を直接注入したり、皮膚に塗布して浸透させたりする方法をとることもあります。
血管の剖出と切開部の縫合
上記で述べた動脈と静脈を取り出すために、血管を覆っている疎性結合組織や脂肪組織を取り除く必要があります。この作業は解剖で行う「剖出」と同じです。該当箇所に2~3cmほどの切開を行い、血管を剖出します。薬液の注入と排血が完了した後は、最終的に切開部を縫合し、テープや修復用ワックスなどで目立たないように隠します。
胸水や腹水、体腔内残渣物などの吸引と薬液充填
さらに、脈管からでは対応しきれない部位にある胸水や腹水、胃の内容物、尿、便などを吸引します。腹部に1cm程度の穴を開けて、体腔内に残った腐敗要因となる物質を除去します。吸引後は、同じ場所から直接薬液を体腔内に充填します。
なお、エンバーミングで使用する薬液には、特殊なケースにも対応できるよう、さまざまな種類があります。状況に応じて、最適な薬液をそのつど選択しています。
- 組織の保湿や水分補給効果がある薬液
- 脱水や乾燥を促す薬液
- やつれてしまった部位に組織の代わりとして充填する薬液
- 欠損箇所を補うためのワックス など
最後に、全身を洗浄します。
ここまでの処置は、あくまで「ご遺体の保全」を目的とした、エンバーミングならではの内容ですが、エンバーマーの仕事はそれだけではありません。
着せ替えや表情の再調整、ヘアセット
われわれエンバーマーが、ご遺族と接することができる時間はあまり長くはありませんが、その中でできる限り、ご遺族の要望や故人への想い、エンバーミングに期待していることなどを教えていただきます。その情報に基づいて、故人の表情や髪型を整えたり、衣装の着付け、ひげや爪の手入れ、化粧を施したりします。
そのため、エンバーミングのご依頼時には、故人についての具体的な情報のご提供をお願いしています。
エンバーミングの依頼に必要なもの
エンバーミングを依頼する際は、「死亡診断書(検案書)のコピー」と「エンバーミング依頼書」(以下、依頼書)の2点が必要です。また、故人に着せたい衣装や生前の写真、場合によっては入れ歯やウィッグ、アクセサリーなどをお預かりすることもあります。
依頼書には、ご遺族の要望を記入する欄があり、表情の整え方、ひげ剃りの要・不要、髪型、服の着せ方、メイクの希望などをご記入いただきます。内容によっては、高度な修復が必要になることもあります。
なお、依頼書には、2親等以内のご遺族による署名が求められます。
ご家族が立ち会えないからこそ依頼書が必要
エンバーミングでは、先述したような外科的な処置に加えて、ホルマリンを始めとする医薬用外劇物の使用を伴います。また、死亡診断書に記載された死因だけでは分からない、何かしらの感染症に故人が罹患している可能性もあります。こういったことを考慮し、エンバーミングは曝露対策や感染防御、故人のプライバシーに最大限配慮された「エンバーミングセンター」という専門の施設で行われます。
またエンバーミングは「日本遺体衛生保全協会」の認定資格を持つ専門のエンバーマーが実施するものであり、原則としてご遺族を含む第三者が立ち会うことはできません。
このような事情から、故人のお姿をご遺族の希望に近づけるためにも、依頼書の質問にお答えいただくようにお願いしています。
最後に
エンバーミングの依頼は、特別な場合に限られたものではありません。最近では、「できるだけゆっくりと故人と過ごす時間をとりたい」「冷たくて重たそうなドライアイスをあの人の身体に乗せるのはかわいそう」「病気でやつれた顔を元気な頃のようにきれいにしたい」といった想いから、エンバーミングに価値を感じて依頼されるケースも増えています。
エンバーミングの一番の目的は、故人のお身体の状態を安定させることによって、ご遺族が安心して最後のお別れに向き合えるように時間を確保することだと考えています。そして、「大切な人の死」という現実を受け入れ、気持ちの整理をするための時間と場を提供するグリーフサポートの一環であると考えます。
担当するエンバーマーは、責任をもって、書類や写真を参考にしながら、目の前のお身体に向き合います。最後の時間に、ご家族が「大切な人にどのような姿でいてほしいか」「故人はご家族とどのようなお姿でお別れしたいか」を想像しながら、エンバーミングの処置を行っているのです。
執筆:牛渡 一帆(うしわた かずほ) 株式会社ジーエスアイ エンバーミングセンター長 一般社団法人日本遺体衛生保全協会(IFSA) 認定エンバーマー、スーパーバイザー 一般社団法人グリーフサポート研究所認定 グリーフサポートバディ 2011年にIFSAのエンバーマーに認定。2012年に株式会社ジーエスアイに入社。 2020年、厚生労働行政推進調査事業費補助金新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「遺体における新型コロナウイルスの感染性に関する評価研究」に参加。エンバーミングの普及に努める。 編集:株式会社照林社 |